巨龍のあくび
第59回:アメリカ映画「黒獅震雄風」
自分の好みを勝手に披露して恐縮だが、国内外で好きな俳優といえば、女優はキャサリン・ヘップバーン、男優は三船敏郎とショーン・コネリーである。むかし銀行の入社試験願書に尊敬する人物としてキャサリン・ヘップバーンと書いた記憶がある。試験官も困っていたようだ。それはさておき、男優の二人には共通点がある。彼らは喜劇俳優としても歴史に残る大俳優になれただろう。「七人の侍」で三船敏郎演じる菊千代は勘兵衛(志村喬)の強さに惹かれて勝手についてくる狼のような乱暴者であり、劇中では一本調子で怒鳴っているばかりだが、彼が吠えながら目まぐるしく変える表情や仕草の可笑しみは天下一品である。
ショーン・コネリーも同様だ。米映画「史上最大の作戦(62年)」はジョン・ウェイン、ロバート・ミッチャム等をはじめとするオールスターで固められた豪華映画であり、ここに脇役の一人として当時無名のショーン・コネリーがノルマンディー上陸コマンド部隊の一兵卒として登場する。この痩身長躯の兵隊は見かけに似合わずドジで上陸を果たした途端に水際で派手に転倒する。ほうほうの体で上陸したビーチは混乱の坩堝で、そのなかを自転車に乗りヘルメット姿の市長が大喜びでシャンパンを片手に出迎える。その横では何故かブルドッグを連れたイギリス軍中佐が車両部隊を陣頭指揮しており、エンジンが故障した装甲車を「うちの婆さんだったらこうするね」と言いながら杖でひっぱたき、何と直してみせる。こんな不思議な光景を茫然と眺めながらショーン・コネリーと相棒が「I tell you, there are some pretty peculiar blokes on this beach.(おいおい、この海岸にいるのは変な奴ばかりだな)」とぼやく場面は何度見ても吹き出してしまう。
ショーン・コネリーの最高傑作は「風とライオン(75年)」だろう。むかし上海で「黒獅震雄風」という映画を見たらこの作品だったことがある。中国語の吹き替えで鑑賞しても素晴らしい作品だが、ショーン・コネリーが「ライライ〜シェシェ!」と中国語を喋るのだけは見るに堪えなかった。この映画で彼は預言者ムハンマドの血を引き砂漠に生きるリフ族の首領ライズリ役を演じている。この作品は実話が下敷きになっており、日露戦争の始まった1904年、アフリカ・モロッコの港町タンジールで米国人ペデカリス夫人(キャンディス・バーゲン)とその子供がライズリたちの一団に誘拐される。当時のモロッコはヨーロッパ諸国に蹂躙されつつあり、ライズリは先祖の地を守るため、彼女たちを人質にして欧米の列強と渡り合うための切り札にしようとする。アメリカ人誘拐の一報はアメリカ合衆国第26代大統領セオドア・ルーズベルト(ブライアン・キース)に報告され、大統領は国威発揚、モロッコ進駐、そしてきたる大統領選挙を総合勘案し即座に出兵を決意する。「アメリカ人の生命と財産を保全すべく大西洋艦隊を派遣する。合衆国の選択肢はペデカリス夫人を生きて返してもらうか、そうでなければライズリを殺すのみである」と彼は宣言する。
ここから先はハリウッド一流の手に汗握る大活劇。戦闘と交渉の結果、遂にライズリは交換条件に応じ、ペデカリス夫人を釈放し海兵隊のジェローム大尉に引き渡すが、彼は裏切りによりドイツ軍に捕らえられてしまう。いつの間にか彼に惹かれるようになっていた彼女はこれに憤激し、ジェローム大尉にナイフを突き付けてライズリ救出を迫るが、大尉は「口でおっしゃればそれで良いのに」と悠然と笑い飛ばし、不利な戦いを即座に承諾する。いまの日本人はいざ知らず、米国人にとって誇りと責任は生命より大切なのである。 この映画には侠気というか男の矜持を感じさせる名場面が随所にちりばめられている。ジョン・ミリアス監督は黒澤監督の大ファンであったようで黒澤映画へのオマージュも登場する。半月刀を構え不敵に笑いかけるライズリに対し、ドイツの騎兵将校は拳銃をホルスターに収めサーベルを抜いて一騎打ちを挑む。そしてドイツ将校を倒したライズリは敵の首を討たず高笑いしながら剣を収める。黒澤映画「隠し砦の三悪人」における三船敏郎と藤田進との一騎打ちがそれである。
この映画の政治的背景は、民族自決を求める地元勢力と、帝国主義に猪突突進する列強との葛藤であり、アメリカの立場からいえば、加えて蛮族に近代文明の優位さを見せつけようという狙いがあっただろう。そしてそれから100年後、アメリカはその傲慢さのツケをアフガンやイラクで払うことになる。
しかしながら国際紛争において大義とは所詮は自国民向けの政治宣伝であり、善悪を主張しあっても始まらない。この映画で誰もが感銘を受けるのは、周りから嫌われつつも国益を追求し大西洋を挟んで対峙するリフ族首長とアメリカ大統領の信念と存在感、そして困難な境遇にあっても気品を保ち毅然とした態度を失わない米国人女性、この三人の生きざまである。首長と大統領は一度も対面することはないのだが、戦いを通じて互いに尊敬と友情に似た感情が芽生えるところが「敵は敵を知る」道理なのである。この映画の最後はセオドア・ルーズベルトがライズリから届いた手紙を読む場面で終わる。彼は自分がハンティングで仕留めた熊の剥製の前で人払いして読み始める。「貴殿は風、我はライオン。貴殿は嵐を巻き起こし、 砂塵は我の目を刺し大地は乾ききっている。我はライオンの如く己の場所に留まるのみなれど、貴殿は風の如く留まるところなし」
熊のぬいぐるみのテディ・ベアは狩猟が好きだったセオドア(テディ)ルーズベルトのスポーツマンシップに由来するといわれており、また彼は時の氏神としてポーツマスで日露戦争の調停役を買って出た人物として日本は好意的に見られているが、国際政治の舞台における彼の手法は砲艦外交(棍棒外交)に尽きる。米西戦争以降の米国外交の指針となっていたモンロー主義に基づき、西半球に積極的に介入した強面の人物である。当時のルーズベルトはヨーロッパ諸国やコロンビア、キューバ等から蛇蝎の如く嫌われた人物だが、敵国の大物指導者として、その政治手腕は誰もが認めていた。国際政治とは自国の権益の主張合戦であり、意見を持たない人物に対して、敵対する国は尊敬するどころか、意見の相違点を見出すこともできない。国内外からどれだけ罵声を浴びせられても頑として自国の権益を主張する人物こそが真の政治家であり、当事者間の明確な主張と論点の存在こそが結果的には世界の平和に資するのである。平和の実現を目的とした軍縮や宥和政策が不幸な戦争を招いた例は歴史にいとまがない。
暑い八月を迎え、わが国の砲艦外交ならぬ幇間外交に眩暈を覚えつつ書いた拙文だが、今日8月25日がサー・トーマス・ショーン・コネリー80歳の誕生日であることに免じ、失礼の段ご海容賜りたい。(了)
文中の見解は全て筆者の個人的意見である。
平成22年8月25日
杉野光男(東洋証券 主席エコノミスト)
【経歴】
- 1974年
- 一橋大学商学部卒
- 同年
- 三菱信託銀行入社
- 1981年
- 上海華東師範大学へ留学
三菱信託銀行北京駐在員、上海駐在員事務所長、中国担当部長を経て2007年より現職 - 著書
- 「日本の常識は中国の非常識」(時事通信社)
「中国ビジネス笑劇場」(光文社) 等
- 【ひと言】
- さまざまな矛盾を内包しつつ驀進する中国。その素顔をメディア情報だけでなく、現地取材、ネットや口コミ情報も交え楽しくお伝えできればと思います。腹を抱えて笑うジョークの中に、しばしば今の中国を理解するキーワードが潜んでいるものです。
- ご投資にあたっての注意事項
-
手数料等およびリスクについて
- 株式の手数料等およびリスクについて
- 外国株式等の売買取引には、売買金額(現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対して最大 0.8400%(税込み)の国内取次ぎ手数料をいただきます。外国の金融商品市場等における現地手数料や税金等は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
- 外国株式は、株価の変動および為替相場の変動等により、元本の損失が生じるおそれがあります。
- ETF(上場投資信託)は、連動する株価指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。
ご投資にあたっての留意点
- 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
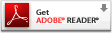
- PDFファイル形式のニュースをご覧になる場合は、Adobe Readerをインストール頂く必要がございます。
Adobe Readerダウンロードページへ



