タカ派に転換したECB
3/10に開催されたECB理事会で、ウクライナ問題の欧州経済への影響に強い警戒感が示され、ユーロ圏の2022年インフレ率予想は3.2%→5.1%へ上方修正された。
これと同時に示されたのが、量的緩和政策の縮小加速の方針。物価状況に依拠する面もあるが、従来は債券購入量を200億ユーロに減額する時期を10月としていたが、6月に前倒し。早ければ7~9月にも量的緩和政策を終了し、年内の利上げが視野に入った。
ECBのラガルド総裁は昨年末時点で2022年内の利上げに関し「とてもありそうにない」と語っていただけに、この決定は予想外のタカ派転換となった。
米国の利上げ加速を後押しも?
ECBによる今回の方針転換は、米国の金融政策正常化を加速させる要因ともなろう。FRBは3月会合で25bpsの利上げを決定し、1回25bpsの利上げを年内は計7回実施する見通しを示した。2023年も3~4回を見込み、政策金利は中立金利を上回る水準を想定。
米国の主要経済指標で、2月雇用統計で平均賃金は伸びが鈍化した一方、2月CPIは伸びが加速し、イエレン米財務長官をして「不快なほど高いインフレ」と言わしめた。昨今の国際情勢が及ぼす影響次第では正常化ペースが緩やかになる可能性は残るものの、今後のECBの決定が米国の金融政策に何らかの影響を及ぼしてもおかしくはないだろう。
日本は唯一のハト派に
このように正真正銘、(便宜上中国を除けば)世界的に金融緩和の正常化へ舵が切られている。こうしたなかで、主要国で唯一と言って差し支えないくらいにハト派スタンスを維持しているのが、日本だ。
1月の日銀金融政策決定会合後の定例会見で黒田日銀総裁は、「生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、拡大方針を継続」する旨を改めて明示。併せて開示した最新の展望レポートにおいても、2022年度及び2023年度のCPIの見通しを10月時点から上方修正したものの、上限でもそれぞれ+1.2%、+1.3%に留まり、目標とする2%には程遠い状況が継続する見込みである。
もっとも、市場では警戒感が渦巻き初めているように見えるのも事実。黒田総裁の任期が2023年4月に切れることを踏まえ、これ以降に政策変更があるのでは、という見方である。変動金利と固定金利を交換する金利スワップのOIS市場では、マイナス金利導入後初めて1年後からの1年間の短期金利の予想(2023年2月からの1年間を対象とした契約)がプラス圏に浮上したという。
とはいっても、今後1年間は主要国で唯一と言ってよい程、緩和的な相場環境という前提が日本株には維持される見込み。古くからの諺だが、「残り物には福がある」。マーケットにも当てはまらないとは限らないとみたい。
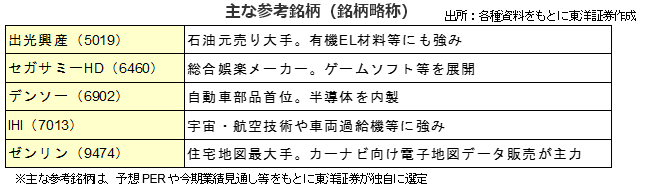
(マーケット支援部 山本)



