立体物を「印刷」する
2次元の紙面を印刷するのではなく、3次元の立体物を印刷する3Dプリンター。その裾野がじわり拡大してきている。
そもそも3Dプリンターとは、3DCADの設計データをもとに、スライスされた2次元層を1枚ずつ積み重ねて立体モデルを製作する機械を指す。この「積層方式」が基本方式だが、液状樹脂を紫外線で少しずつ硬化させる「光造形方式」や、熱で溶かした樹脂を積み重ねる「FDM方式」といったような様々な方式も存在する。
ものづくりを支える縁の下の力持ち
3Dプリンターのメリットとしてよく指摘されているのが、コスト削減や工程短縮といったような生産の効率化だ。構想に始まり、設計・シミュレーション、製造シミュレーション、製造、保守サービスに至るあらゆる工程を3Dデータで行い、工程期間の短縮化や多品種少量生産等を可能にすることで、製造業での3Dプリンターの活用が急速に進んでいるとのこと。3Dプリンターが製造業に及ぼすインパクトを代表し得る言葉を紹介すれば、①後工程の負荷を前倒しするfront-loading(設計しながらデータを形にして検証する)、②短期間で試作するRapid Prototyping、③型や治具等を短期間でつくるRapid Tooling、④データから直接製品をつくるRapid Manufacturing等がある。
もっとも、製造業(の製造工程)での活用は3Dプリンター市場の拡大の端緒でしかないだろう。現に、最終製品の事例が出ている他、個人が家庭で手軽に造形を楽しめるようになっているようだ。。3Dプリンターでの制作例としては、ジェットエンジン部品やオーダーメイドの矯正用マウスピース、人物のフィギュア、電池、LEDライトと様々だ。さらには、食品そのものの「印刷」や、家やオフィスといった建造物そのものの「印刷」の事例があり、目が離せない状況だ。
ついに医療用分野での実用化へ
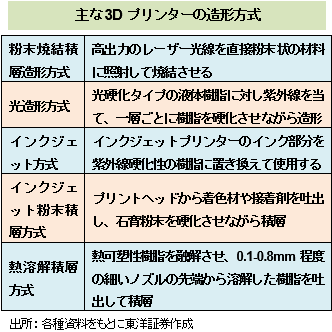
着々と応用分野が広がっている印象の強い3Dプリンターだが、足もとでは、細胞を使って人工的に組織を作り出す「バイオ3Dプリンター」が実用化の段階に入っているようだ。
例えば、複写機大手のリコーは、自社開発したバイオ3Dプリンターで、新薬の安全性評価のためのチップ製品を事業化して複雑な組織の作製を目指す模様。また、富士フィルム等が出資しているサイフューズというスタートアップは、佐賀大学等と人工血管の臨床研究を開始し、2020年代前半には事業化を見込む。バイオ3Dプリンターが人工臓器の作製に使われると期待されているようだ。
一部では2021年には2016年の3倍超の、約13億ドル規模へと成長すると期待されるバイオ3Dプリンター市場。3Dプリンター全体にどのような変化を及ぼすのだろうか。
主な関連銘柄(銘柄略称)
主な関連銘柄としては、日本株ではJSR(4185)、キーエンス(6861)、図研(6947)、リコー(7752)、米国株ではジョンソン&ジョンソン(JNJ)、ストラタシス(SSYS)などが挙げられよう。
(マーケット支援部 山本)



