民間主導の宇宙開発へ一歩
時代が令和に替わった10連休中の5/4、インターステラというロケット開発スタートアップが小型観測ロケット「MOMO」3号機の打ち上げに成功した。
これは国内で初めて民間企業が単独で開発したロケットが宇宙空間に達した事例であり、従来の国主導での宇宙開発を変えるとされる。
今後は、小型衛星を搭載可能なロケット「ゼロ」を開発し2023年の打ち上げ開始を目指す模様。
様々な民間企業が取り組む宇宙活用
日本勢が取り組む主な宇宙開発の事例としては、人工衛星等から発生する宇宙ゴミ「デブリ」の除去や宇宙旅行の実現、人工衛星の信号を活用した正確な位置情報の配信、(成層圏ではあるが)「空飛ぶ基地局」の構築を通じた地上よりも広範囲を安価に網羅できる通信基地局の構築といった具合だ。
上記の点では、例えばANAやエイチ・アイ・エスが国内唯一の有人宇宙機開発会社PDエアロスペースと宇宙旅行実現に向け提携したり、ソフトバンクグループが月や地球の周りに張り巡らせた人工衛星で、地球上のどこにでもインターネットの高速通信を提供することを目指す、米衛星通信ベンチャーのワンウェブに出資したりといった具合だ。
また、宇宙空間を活用するのに必要なインフラの土台の整備にも取り組んでいる。企業が小型ロケット事業を展開するには発射場を整備し打ち上げの頻度を高めることが欠かせないとされるためだ。これに関しては、例えばキヤノン電子やIHIエアロスペース、清水建設等が出資するロケット会社スペースワンが、日本初となる民営ロケット発射場を建設する見通し。
日本における民間企業による宇宙開発は、ベンチャー等の新興勢が主な担い手であり、そこに大手企業が出資や提携を通じて協力する構図の印象だ。
世界でも宇宙活用への取り組みが進む
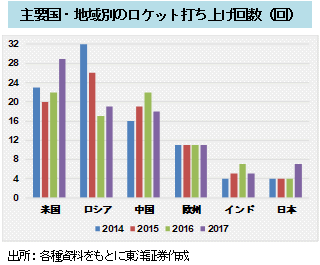
もちろん、宇宙開発に積極的に取り組むのは日本だけではない。世界の様々な企業が攻勢をかけている。
例えば、宇宙開発ベンチャーのブルーオリジンを設立したジェフ・ベゾス氏が経営する米アマゾンは人工衛星を使ったブロードバンド通信サービスへの参入を目指している他、イーロン・マスク氏率いる米スペースXも同様の構想を表明。中国政府が宇宙産業を重点領域に位置付けた「中国製造2025」を背景として、小型ロケットを手掛ける重慶零壱空間航天科技や中型ロケットを手掛ける北京藍箭空間科技といった宇宙スタートアップが躍進している様子。
もちろん、ロケット開発・打ち上げのみならず、衛星画像データの提供サービスや成層圏含めた宇宙空間での通信網構築、宇宙旅行の実現といった様々な分野で米・中・欧州等の様々な企業が積極的な取り組みを推進している。
日本勢が今後宇宙開発分野で主導権を握れるか。ますます目が離せない。
主な関連銘柄(銘柄略称)
主な関連銘柄としては、清水建(1803)、カーリットHD(4275)、ソニー(6758)、キヤノン電(7739)、ANA(9202)などが挙げられよう。
(マーケット支援部 山本)



