拡大続けるEC市場
EC(電子商取引)の市場規模は拡大を続けている。経済産業省の資料によれば、世界のEC市場規模(BtoC)は、2018年には2.84兆ドルとなっており、2021年には4.88兆ドルにまで拡大し、2桁成長が続くとみられているようだ。国別(2018年時点)でみると、中国がトップでその規模は2位の米国の約3倍にも及ぶ。米国の次には英国、日本が続く。
国境を跨いだ、いわゆる越境ECの市場規模も2桁成長が続き、2018年時点には6760億ドル、2020年には9940億ドルに伸びる見通しとのこと。
リアル×ネットの起爆剤?
足もとではIoTといった言葉が体現するように、リアル空間とネット空間の垣根が形骸化し、融合のペースが進んでいるようだが、この原動力となったのがECの勃興ではないかと考えられる。象徴的なのが、アマゾンのようなEC事業者の台頭と、リアル事業者の取り組みだ。あのアマゾンの存在感の巨大さはさることながら、ウォルマートがEC分野に取り組む他、セブン&アイは実店舗やECサイト等の全てのチャネルを統合連携させてアプローチするオムニチャネル戦略を掲げている。
また、ECが実店舗を淘汰しているわけではないということにも注目だ。一部では、米国ではオムニチャネルを有効活用することで実店舗の売上が伸びたとの指摘がある。加えて、アマゾンが米国の一部地域で無人コンビニや書籍専門型実店舗といったリアルへの取り組みを進めている他、中国家電量販大手の蘇寧易購集団が日用品・食品分野を強化すべく大型スーパー中心の仏カルフール中国事業を買収するといった取り組みからも、実店舗が依然重要なことが推察されよう。また、米国百貨店大手メーシーズによれば、ネット通販の伸びと同時に、実店舗販売は「改善している」模様。
寡占化の批判は本当なのか
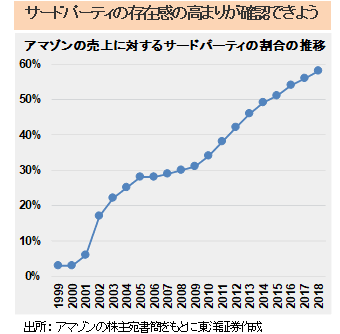
ここで、ECといえば誰でも頭に浮かぶであろうアマゾンについて考えてみたい。同社には独占的な立場等の観点から、各国の独禁法当局が厳しい目を向けているとみられる。が、本当にそうなのだろうか。面白いデータがある。
同社が今年公表した株主宛書簡によれば、同社のECサイト上での売上に占めるサードパーティ(ほとんどは外部の独立した中小規模の小売事業者)の割合は、2018年時点では、58%と過半数を占めているとのことだ。約20年前の3%からは大きく伸びている。同社は中小EC事業者向けの短期融資サービスを展開しているが、これが寄与した可能性も考えられるのではないか。もしかしたら、巨大なプラットフォーマーがあってこそ、EC市場の成長が実現されたのかもしれない。
主な関連銘柄(銘柄略称)
主な関連銘柄としては、日本株では7&I-HD(3382)、ネットイヤー(3622)、楽天(4755)、米国株ではアマゾン(AMZN)、アリババ ADR(BABA)、ウォルマート(WMT)、中国株では蘇寧易購集団(002024)などが挙げられよう。
(マーケット支援部 山本)



