人類の歴史に「お酒」あり
仕事の後の一杯が生き返る!そんな経験をお持ちの方も少なくはないだろう。
日々の疲れを吹き飛ばしてくれる妙薬は一般的には4000年前のシュメール文明時代に遡るとされる。発掘された遺物には当時の人々のビール造りの模様が記録されていたようだ。また、紀元前後に最盛期を極めたローマ帝国時代には南欧を中心に葡萄酒(ワイン)の醸造が盛んに行われた。
また、世界の様々な地域で様々な種類のお酒が愛飲された。一例を挙げれば、スコットランドのウイスキー、ロシアのウォッカ、カリブ海域のラム酒、中国の白酒、日本の日本酒といった具合。歴史を通じて、人々の生活にお酒は密に関わっていたことが読み取れよう。
健康意識の高まりとお酒に抱く印象
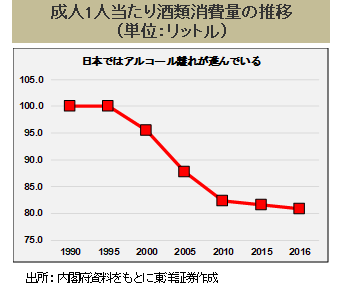
もっとも、ここ近年では、お酒に対する意識が変わっているようだ。世界のアルコール消費量は減少に転じているようであり、ウォッカを大量に消費しているとのイメージもあるロシアでもウォッカ離れが進んでいるという。
最大の要因と思われるのが、健康意識の高まりだ。過度な飲酒は臓器や精神面への悪影響を及ぼしうる。脂肪肝や肝硬変等の肝臓障害、糖尿病やすい炎等のすい臓の障害、消化管、循環器系、さらには脳や末梢神経障害といったように、全身の臓器に悪影響が及び、付け加えると、アルコール依存症による社会への影響も根強く指摘される。
また、「酔っ払うと格好悪い」「太りそう」といった否定的な見解や世代間での価値観の相違、さらには若者の相対的な所得の低下といったことも重なって若者を中心にお酒離れが顕著なようで、酒類メーカーとしても厳しい立場に置かれているのが現状のようだ。
巻き返しを図る酒類メーカー
もちろん、酒類メーカーも対策に走っている。健康志向に対応した製品や、低アルコール度数のもの、果物や野菜でできたフルーティーなお酒等、トレンドを捉えた商品の開発が進み、近隣スーパー等の店頭でそういった類の商品を目にする機会も多くなってきた。
例をあげると、糖質ゼロ・プリン体ゼロのビール系飲料、低価格で流通する第3のビール、炭酸ガスを閉じ込めシャンパン感覚で楽しむ生酒、すりつぶした苺を仕込んだにごり酒、日本酒と薔薇がコラボしたリキュール、健康に良い豆乳で造った日本酒といった具合だ。
そうしたいわゆる新世代向けのアルコール飲料の市場規模は比較的小さいとの指摘はあろうが、時代の変化に適応すべく行う企業努力は素直に評価すべきだろう。
主な関連銘柄(銘柄略称)
主な関連銘柄としては、日本株ではアサヒ(2502)、キリンHD(2503)、宝HD(2531)、サントリーBF(2587)、中国株では貴州茅台酒(600519)などが挙げられよう。
(マーケット支援部 山本)




