特集
自然災害史としての「平成」時代
平成も残すところ僅かとなったが、この時代は自然災害に悩まされたといっても過言ではなかろう。
地震だけで見ても、1995年の阪神淡路大震災、2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震と、稀に見る規模の大災害が平成に集中。他にも、豪雨による洪水被害や土砂被害、火山活動に伴う火砕流被害等、自然現象に基づく被害が、平成には相次いだ。
強くてしなやかに、「国土強靭化」
相次いだ自然災害により受けた被害、また、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震や首都直下地震を受け、2013年12月には「国土強靭化政策大綱」が策定された。
同大綱においては主に、理念として①人命保護、②公共施設の被害の最小化、③迅速な復旧復興が、基本的な方針として①ハード対策とソフト対策の組み合わせ、②民間資金の積極的な活用、③「自律・分散・協調」型の国土の形成が、配慮すべき事項としては民間投資の誘発や五輪等に向けた対策が掲げられている。
また、国土強靭化の推進方針(分野別)においては、住宅・都市では密集市街地の火災対策、エネルギーでは地域間の相互融通能力の強化、情報通信では長期電力供給停止等に対する対策の早期実施、産業構造では企業連携型BCP/BCM(事業継続マネジメント)の構築促進、交通・物流では交通・物流施設の耐災害性の向上が挙げられている。
民間企業なくして強靭化なし
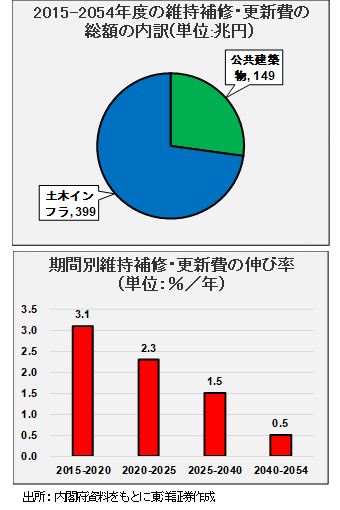
2019年度においては、国土強靭化関係予算案全体額として5兆3056億円(うち公共事業関係費4兆2682億円)が提示された。
もっとも、老朽インフラの維持補修・更新費が2015-2054年度の期間で総額547兆円にものぼると試算されていることから、国土強靭化に
係る総合的な費用は天文学的な数字になる可能性が高い。
そこで期待されるのが、民間企業の役割だ。国土強靭化は建造物や土壌の強化等にとどまらず、通信インフラの保守や物流網の維持、避難時の生活支援等、非常に幅広い領域にまたがることが予想できよう。そうである以上、幅広い業種に係る民間企業の持つノウハウを活用することが、国土強靭化を早期に達成する一番の近道となろう。
主な関連銘柄(銘柄略称)
主な関連銘柄としては、大林組(1802)、熊谷組(1861)、協エクシオ(1951)、デンヨー(6517)、東ガス(9531)などが挙げられよう。
(マーケット支援部 山本)




