逆説的な最低所得保障
国際社会には様々な問題があるとはいえ、世界経済は拡大基調にある。ただ、貧富の差が拡大していることに対する批判も根強い。そんななか、欧州で活発に議論され始めている社会保障制度がある。それは、「ベーシックインカム(BI)」と呼ばれる。
BIとは、国がすべての国民に無条件で毎月一定額を一律に支給するというものであり、格差是正や失業対策になるとして期待されている。現在、世界で唯一、フィンランドが実験的に導入しているようだ。
フィンランドにおけるBI導入実験
同国が実験に踏み切った背景として、福祉政策が充実していながら失業率が高止まりし社会福祉の手続きが複雑化していることが指摘されている。実験は2年間、毎月約7万円を失業者2000人に支給するという内容で、いくら働いても支給額が減額されることはないという。従来の失業手当では収入を得ると減額されるため働く意欲の障害になっていたが、このBIによって、働いた分が安定収入に上乗せされる形になるため、働く意欲の促進剤となり苦しい生活から脱することができたとの報告があり、BIが今後広がっていくと見込む向きも根強い。
ただ一方で、財源確保の問題や、勤勉さや働く意欲が喪失するといった反対論もあり、実際にスイスでは国民投票で導入が否決された。
BIが注目されている背景にAIあり
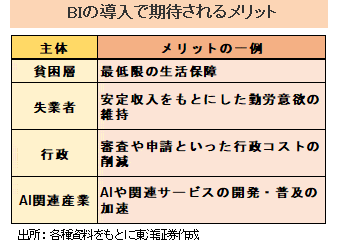
BI導入の議論が活発化している背景として根強く指摘されているのが、人工知能(AI)の台頭だ。特段新しい話ではないとはいえ、足もとで我々を取り巻く様々な場所でAIが活用されている。例えば、物流センターでの荷物の運び出しや、牛丼店等の飲食店での業務補助、ラジオ局でのアナウンサーに代わっての原稿読み上げといった具合だ。これが発展していけば、
独創性を求められない単純労働の担い手は、AIによって置き換えられていくかもしれない。
AIが失業を促すとも揶揄される現状を受け、大手ハイテク企業幹部をはじめ歴史学者のような有識者たちが一斉に「BIを検討すべき」旨の発言をしている。その裏には、AIによる失業=収入源の喪失という図式が無くなれば、AIが受け入れられる余地は大きくなるだろうという思いが見て取れよう。ちなみに、グーグルのエンジニアで未来学者のカーツワイル氏は、意味と目的を懸念材料としながらも、2030年代前半には先進国で、2030年代末には全世界でBIが導入されていると予測しているようだ。
確かに、BI導入を巡り、指摘されるような懸念は根深いものである。とはいえ、先述のフィンランドに続き、(規模は劣るものの)自治体やNGO等が主導し、10余りの国や地域でBIの実証実験が行われているようだ。
AIに対する懸念を払拭し、AIの公正な発展を促すためにも、BIの導入は避けて通れないものとなる可能性は高いだろう。
主な関連銘柄(銘柄略称)
主な関連銘柄としては、DMP(3652)、ALBERT(3906)、メタップス(6172)、SMN(6185)、富士通(6702)などが挙げられよう。
(マーケット支援部 山本)




